
「ZEH(ゼッチ)」という言葉を耳にする機会が増えましたが、そのさらに先を行く「LCCM住宅」をご存知ですか? これは、家の一生を通じてCO2排出量をマイナスにする”究極”のエコ住宅です。 この記事では、LCCM住宅の基本からZEHとの決定的な違い、気になるメリット・デメリットまで、わかりやすく解説します!
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。
LCCM住宅とは?まずは基本を理解しよう
LCCM住宅は、環境への配慮を究極まで高めた「未来の家」の姿です。
多くのエコ住宅が住んでいる間のエネルギー収支に着目するのに対し、LCCM住宅は家が建てられてから解体されるまでの一生(ライフサイクル)を通じて、CO2排出量をマイナスにすることを目指します。
つまり、消費するエネルギーを太陽光発電などで創り出すだけでなく、建設時などに排出したCO2すらも相殺してしまう、まさに究極の脱炭素住宅なのです。
LCCM=ライフサイクルカーボンマイナスの略
LCCM(エルシーシーエム)とは、「Life Cycle Carbon Minus(ライフサイクルカーボンマイナス)」という言葉の頭文字をとった略称です。
「ライフサイクル」は、住宅の建設、居住、そして解体・廃棄までという「一生」を指します。
「カーボンマイナス」は、排出する二酸化炭素(カーボン)の総量よりも、太陽光発電などで削減できるCO2量の方が多い、つまり収支が「マイナス」になる状態を意味します。
この二つを合わせ、「住宅の一生を通じてCO2排出量をマイナスにする家」という意味になります。
「建設」から「解体」まで、住宅の一生でCO2を削減する仕組み
LCCM住宅は、まず高い断熱・気密性能と省エネ設備で、日々のエネルギー消費を最小限に抑えます。
これはZEH(ゼッチ)と同じ考え方です。
その上で、大容量の太陽光発電システムなどを導入し、消費量を上回るエネルギーを創り出します。
この余剰分のエネルギー(CO2削減効果)によって、住んでいる間のエネルギー収支をプラスにするだけでなく、資材の製造や建設時、さらには将来の解体時に発生するCO2排出量までも埋め合わせて、家の一生を通したCO2収支をマイナスにするのです。
LCCM住宅として認定されるための基準
LCCM住宅は、第三者機関による厳格な基準をクリアして初めて認定されます。
認定の基準
認定基準は、次の①②のいずれかを満たすものとします。
①LCCM適合判定ルート
CASBEE-戸建(新築)に基づく、「LCCM住宅部門の基本要件(LCCO2)適合判定ツール」にて評価した計算結果が「適合」である住宅。
②CASBEE認証ルート
CASBEEの戸建評価認証制度に基づき認証された、環境効率ランクがSまたはAであり、かつライフサイクルCO2ランクが、緑☆☆☆☆☆(5つ星)である住宅。
LCCM住宅認定の詳細については、以下をご確認ください。
LCCM住宅とZEH(ゼッチ)住宅の決定的な違い

LCCM住宅とZEH住宅の最大の違いは、CO2排出量を評価する「期間」です。
ZEHが「住んでいる間」のエネルギー収支をゼロにすることを目指すのに対し、LCCM住宅は「建設から解体まで」という家の一生を通じて、CO2排出量の収支をマイナスにすることを目指します。
つまりLCCMは、ZEHの基準をクリアした上で、さらに建設時のCO2も削減する、より上位の究極のエコ住宅と言えます。
LCCM住宅に住む5つのメリット
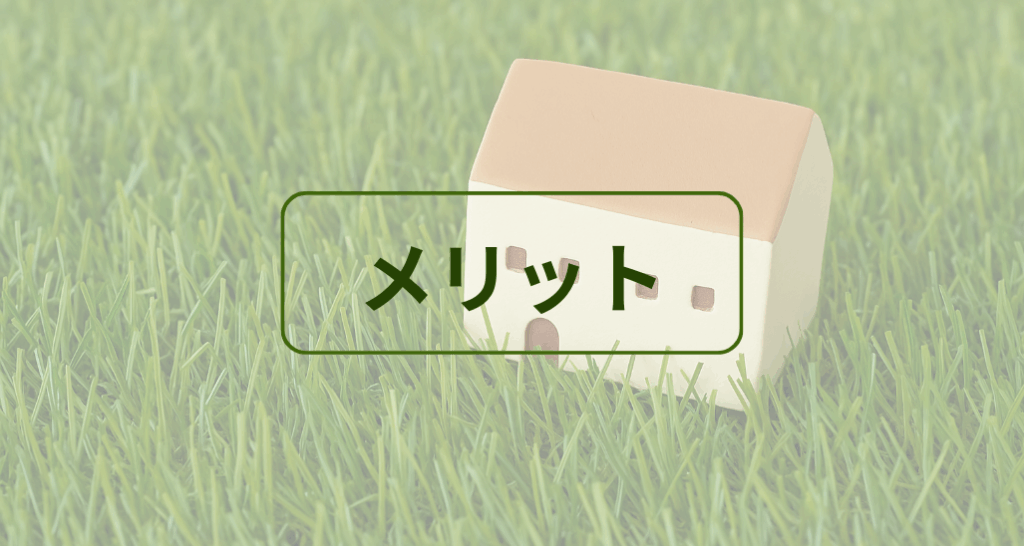
「LCCM住宅」のメリットは、地球環境への貢献だけにとどまりません。
日々の快適な暮らし、光熱費といった経済的なメリット、さらには災害時の安心感まで。未来の暮らしを豊かにする5つの魅力をご紹介します。
メリット①:環境への貢献度が非常に高い
住んでいる間だけでなく、建設から解体までのCO2収支をマイナスにする究極の脱炭素住宅です。
ただ住むだけで、地球温暖化防止に大きく貢献できます。
環境問題への意識が高い方にとって、これ以上ない満足感を得られる住まいと言えるでしょう。
メリット②:光熱費を大幅に削減し、売電収入も期待できる
高い省エネ性能で消費電力を抑え、大容量の太陽光発電で電気を創り出します。
自宅で使う電気を賄えるだけでなく、余った電気は電力会社に売ることも可能です。
月々の光熱費がゼロになるどころか、プラスの収入になることも夢ではありません。
メリット③:高い断熱・気密性で一年中快適な室温を維持
LCCM住宅の前提となる高い断熱・気密性能により、外気の影響を受けにくく、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を実現します。
少ない冷暖房で快適な室温を保てるため、身体への負担が少なく、ヒートショックのリスクも軽減できる健康的な住まいです。
メリット④:災害時(停電時)にも電気が使える安心感
大容量の太陽光発電システムを備えているため、蓄電池を併設すれば、地震や台風などで停電が発生しても電気を使うことができます。
災害時でもテレビやスマートフォンで情報を得たり、最低限の家電を動かしたりできるため、大きな安心に繋がります。
メリット⑤:国から手厚い補助金を受けられる
LCCM住宅は国の脱炭素社会実現に貢献するため、手厚い補助金制度の対象となっています。
「子育てエコホーム支援事業」などでは、ZEH住宅よりも高い補助額が設定されており、高額になりがちな初期の建築コストを大幅に軽減することが可能です。
知っておくべきLCCM住宅のデメリット・注意点
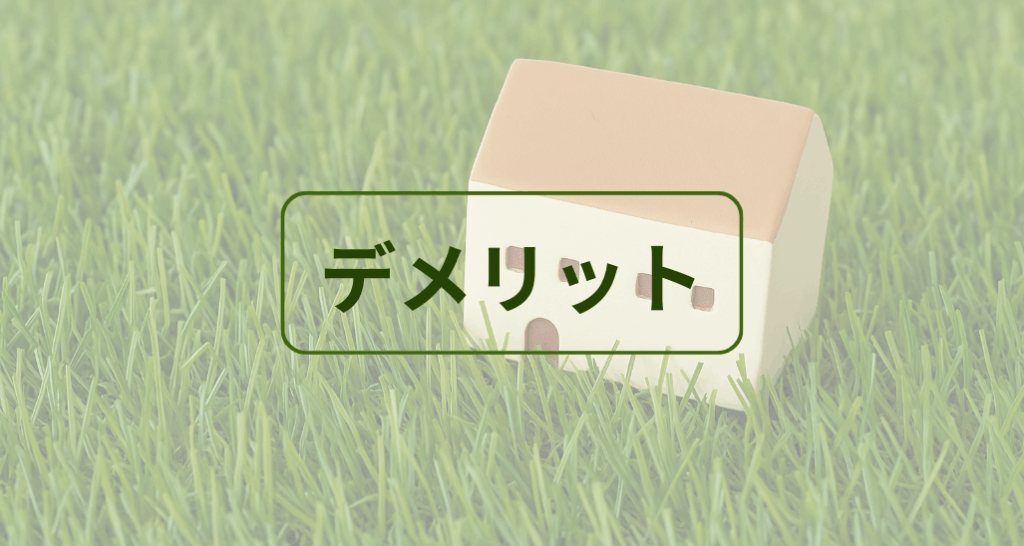
多くのメリットを持つLCCM住宅ですが、計画を進める前に知っておくべき注意点もあります。
高額になりがちな建築コストや設計上の制約など、事前に課題を理解しておくことが、後悔しない理想の家づくりへの鍵となります。
デメリット①:ZEH住宅よりも建築コストが高くなる
ZEH基準をクリアした上で、建設時のCO2排出量も相殺する必要があるため、より高性能な建材や大容量の太陽光発電が必須です。
そのため、一般的な新築住宅やZEH住宅に比べても、初期の建築費用は高額になる傾向があります。
デメリット②:大容量の太陽光発電パネルが必要になる
家の一生で排出するCO2を上回るエネルギーを創出するため、多くの太陽光パネルを載せる必要があります。
そのため、屋根の面積や形状、方角、日当たりなどの条件が厳しくなり、土地によってはLCCM住宅の基準をクリアできない場合があります。
デメリット③:設計・施工できる会社が限られる
LCCM住宅は、省エネ計算に加え、ライフサイクル全体のCO2排出量を算出する専門知識と、それを実現する高い施工技術が求められます。
まだ対応できるハウスメーカーや工務店は少ないため、依頼先の選択肢が限られてしまうのが現状です。
LCCM住宅を建てるためのポイントと流れ

LCCM住宅での暮らしをかたちにするためには、計画的な準備が不可欠です。
信頼できるパートナー選びから始める、理想の住まいを実現するための大切なステップを3つのポイントに絞って解説します。
CCM住宅の建築実績が豊富な会社を探す
LCCM住宅の設計・施工には、省エネ計算やCO2排出量評価などの専門知識が不可欠です。
補助金申請も複雑なため、認定取得や申請手続きに慣れた会社を選びましょう。
過去の実績や建てた家の性能値(UA値・C値)を公開しているか確認することが重要です。
ライフプランに合った資金計画を立てる
LCCM住宅は初期費用が高額になりがちです。
補助金の活用を前提としつつ、住宅ローンに加え、将来の光熱費削減や売電収入まで含めた長期的な資金計画を立てましょう。
無理のない返済計画にすることが、安心して暮らしをスタートさせるための鍵です。
モデルハウスや見学会で性能を体感する
断熱性や気密性がもたらす快適さは、数値だけでは実感しにくいものです。
特に冬場に暖房が控えめでも暖かいか、夏場にエアコン1台で涼しいかなど、実際の建物を訪れて五感で体感しましょう。
空気の質や静かさも、後悔しない家づくりの大切な判断材料です。
注文住宅の性能に関連する他の記事
ZEH(ゼッチ)とは?今さら聞けない基本をわかりやすく解説!
これから家を建てるなら必須!「長期優良住宅」のメリットと申請方法を解説
全館空調とは?基本的な仕組みやメリット・デメリットをご紹介!
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。





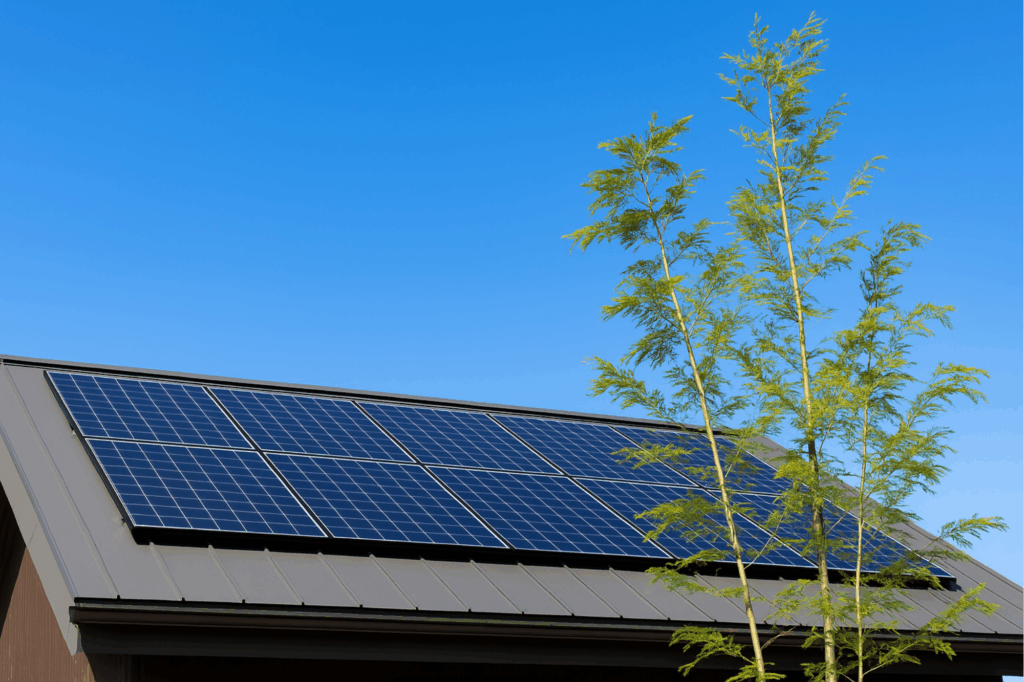



![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)


