
「夏は涼しく、冬は暖かい家」は誰もが憧れる理想の住まい。その鍵を握るのが住宅の「断熱性能」です。 本記事では、高い快適性と省エネ性を両立する「断熱等級6」に注目してご紹介します。 等級5や7との違いから、メリット・デメリットまで、分かりやすく解説します。
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。
そもそも断熱等級6とは?基本をわかりやすく解説

「断熱等級6」とは、住宅の断熱性能を示す「断熱等性能等級」の一つで、2022年10月に新設された非常に高いレベルの基準です。
等級は全部で7段階あり、断熱等級6は上から2番目に位置します。
その性能は、国が省エネ住宅として推進するZEH(ゼッチ)の水準を上回るレベルです。
専門的な基準では「HEAT20 G2」グレードに相当し、少ない冷暖房エネルギーで、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を実現できます。
2025年からの省エネ基準義務化を背景に、将来を見据えた快適でお得な家づくりの新しいスタンダードとして注目されています。
断熱等級6の基準とは?地域ごとに定められた2つの数値
断熱等級6の基準は、家全体の性能を評価するために、主に「UA値(ユーエーち)」と「ηAC値(イータエーシーち)」という2つの数値で定められています。
この基準は全国一律ではなく、日本の気候に合わせて北海道から沖縄まで8つの「地域区分」に分けられ、それぞれの地域ごとにクリアすべき数値が設定されています。
1. UA値 (外皮平均熱貫流率) – 熱の逃げにくさを示す数値
▼どんな数値?
建物の中から外へ「どれだけ熱が逃げやすいか」を示す指標です。この数値が小さいほど、熱が逃げにくく断熱性能が高い家と言えます。
▼何に影響する?
主に冬の暖かさに関係します。UA値が小さい家は、一度暖房で暖めた熱が外に逃げにくいため、魔法瓶のように暖かさを保つことができます。
2. ηAC値 (冷房期の平均日射熱取得率) – 日差しの入りにくさを示す数値
▼どんな数値?
窓などから「どれだけ日差しの熱が室内に入りやすいか」を示す指標です。この数値も小さいほど、日差しの影響を受けにくく、夏を涼しく過ごせる家と言えます。
▼何に影響する?
主に夏の涼しさに関係します。ηAC値が小さい家は、夏の強い日差しによる室温上昇を抑えられるため、冷房の効きが良くなります。
【参考】主要な地域の基準値
多くの住宅が建てられる主要な地域の基準値は以下の通りです。ご自身の地域がどこに当てはまるかで、目指すべき数値が変わります。
| 地域区分 | 主な都市 | UA値 | ηAC値 |
| 1・2地域 | 札幌市、名張市、小樽市など | 0.28以下 | 規定なし |
| 3地域 | 青森市、盛岡市など | 0.34以下 | 規定なし |
| 4地域 | 仙台市、長野市など | 0.34以下 | 2.7以下 |
| 5地域 | 新潟市、宇都宮市など | 0.46以下 | 2.8以下 |
| 6地域 | 東京都、名古屋市、大阪市など | 0.46以下 | 2.8以下 |
| 7地域 | 福岡市、鹿児島市など | 0.46以下 | 3.0以下 |
| 8地域 | 那覇市など | 0.67以下 | 4.6以下 |
※ηAC値は、冬の日射取得が重要になる寒冷地(1〜3地域)では基準がありません。
このように、お住まいの地域で定められたUA値とηAC値の両方の基準をクリアすることで、初めて「断熱等級6」の住宅として認定されます。
断熱等級5や最高等級7との違いは?

断熱等級5、6、7の違いはわかりやすく言うと、「どれだけ少ないエネルギーで快適な室温を保てるか」というレベルの差です。
断熱等級5は、将来の新築住宅の標準となる「ZEH」基準で、一定の省エネ性を確保するレベルです。
断熱等級6は、そのZEHを超えるワンランク上の性能(HEAT20 G2)です。
冬の朝、暖房をつけていない部屋でも室温が13℃を下回らないのが目安とされ、より少ない冷暖房で家中を快適に保てます。
最高等級の7は、暖房にほとんど頼らない暮らしを目指す最高峰の性能(HEAT20 G3)です。
冬でも太陽の熱などを活用し、室温をおおむね15℃以上に保つことを目標としており、世界でもトップクラスの断熱性を誇ります。
性能が上がるほど快適性と省エネ性は向上しますが、それに比例して建築コストも高くなります。
断熱等級6のメリットとは?

断熱等級6は、光熱費削減という経済的利点に加え、暮らしの質を大きく向上させます。
一年中快適な室温の維持、家族の健康促進、そして住宅の資産価値向上などがあります。
ここでは、その代表的な4つのメリットを具体的に解説します。
光熱費を大幅に削減できる
外気の影響を受けにくく、冷暖房の効率が格段に向上します。
魔法瓶のように熱を逃がしにくいため、少ないエネルギーで一年中快適な室温を維持できます。
断熱等級4の住宅と比較して、年間の冷暖房エネルギーを約30%削減できるとされ、光熱費の負担を大きく軽減できます。
家中が一年を通して快適な温度に保たれる
夏は涼しく冬は暖かい、温度変化の少ない安定した室内環境が実現します。
リビングだけでなく廊下や脱衣所との温度差も小さくなるため、家のどこにいても快適に過ごせます。
冬の朝、暖房を付けていない部屋でも室温が13℃を下回らないレベルが目安とされています。
ヒートショックのリスクを減らし健康的に暮らせる
部屋間の温度差が小さくなることで、急激な血圧変動によるヒートショックのリスクを大幅に低減します。
また、断熱性の高さは結露の発生を抑制し、カビやダニの繁殖を防ぐ効果も期待できます。
これにより、アレルギー疾患の予防など、家族が健康的に暮らせる住環境につながります。
住宅の資産価値を維持しやすい
2030年には断熱等級5が新築住宅の最低基準となる予定です。
これからのスタンダードとなる等級5を上回る断熱等級6の住宅は、省エネ性能が高く評価され、将来にわたって資産価値が下がりにくいと考えられます。
長期的に見て有利な選択と言えるでしょう。
断熱等級のデメリットや注意点とは?
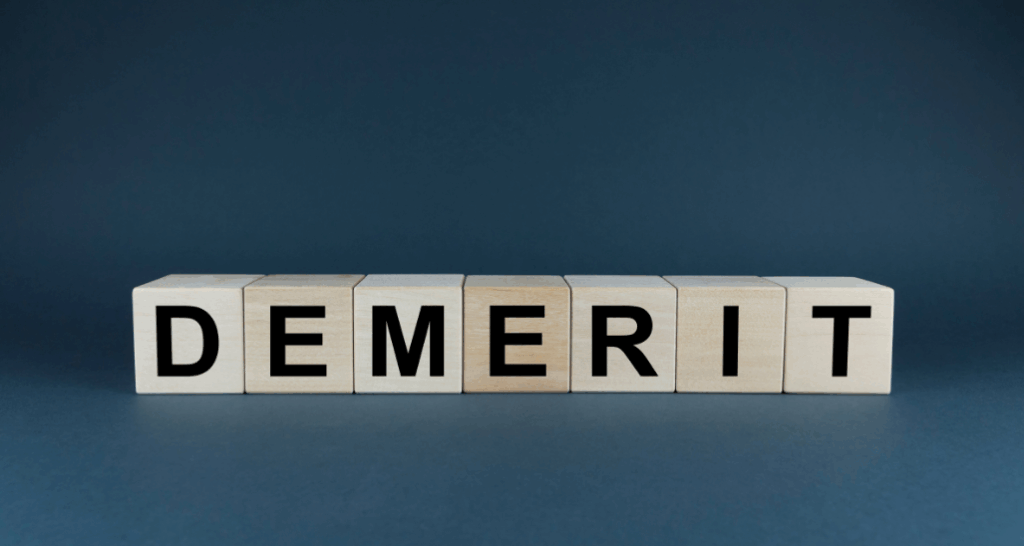
多くの利点がある断熱等級6ですが、導入前に知っておくべき注意点も存在します。
建築コストの問題や、性能を活かすための設計・施工上のポイントなど、後悔しない家づくりのために、事前に確認すべき4つの項目を解説します。
初期費用(建築コスト)が高くなる
高性能な断熱材や熱を通しにくい樹脂サッシの窓、高効率な換気システムなどが必要になるため、建築コストが上がります。
断熱等級5から6へ性能を上げる場合、追加で100万円程度の費用がかかるという目安もあります。
長期的な光熱費削減効果とのバランスを考えることが重要です。
高度な設計・施工技術が求められる
計画通りの断熱性能を発揮させるには、断熱材を隙間なく施工する、気密処理を丁寧に行うといった高度な技術が不可欠です。
設計段階での知識はもちろん、施工会社の技術力によって性能が大きく左右されるため、高断熱住宅の実績が豊富な会社を選ぶことが重要になります。
適切な換気計画が必須になる
断熱等級6の住宅は気密性も高くなるため、意識的に換気しないと空気がこもりやすくなります。
二酸化炭素濃度の上昇やハウスダストの滞留を防ぎ、新鮮な空気を維持するためには、性能に見合った24時間換気システムの導入が不可欠です。
適切な換気計画がないと結露の原因にもなります。
夏の日射対策(日射遮蔽)が重要になる
断熱性が高いということは、一度室内に入った熱が逃げにくいということでもあります。
そのため、夏に強い日差しが窓から入り込むと、室温が上がりすぎてしまい「オーバーヒート」状態になる可能性があります。
庇(ひさし)を深くしたり、窓の外にシェードを設けたりといった日射を遮る工夫が必須です。
断熱等級に関するよくある質問
断熱等級6の住宅は冬でも寒いですか?
いいえ、断熱等級6の住宅は冬でも寒さを感じにくいです。
外気の影響を受けにくく、暖房なしでも室温が13℃を下回りにくいのが目安です。
魔法瓶のように熱を逃がさないため、少ない暖房で家全体を暖かく保つことができ、快適に過ごせます。
断熱等級6は夏はどのくらい涼しいですか?
断熱等級6の家は、魔法瓶のように涼しさが続きます。
たとえば、午前中に一度エアコンで冷やすと、スイッチを切った後も室温の上昇が緩やかです。
外が猛暑日でも、弱い冷房設定で一日中快適に過ごせるほどの性能が目安です。
断熱等級6は2025年に義務化されますか?
いいえ、2025年に断熱等級6は義務化されません。
2025年4月から、すべての新築住宅に義務付けられるのは「断熱等級4」以上です。
これは、これまで最高等級だったものが最低基準となる大きな変更ですが、断熱等級6はこの義務化基準を大幅に上回る、より高性能な任意の基準となります。
断熱等級5の家は不十分ですか?
一概に不十分とは言えませんが、寒冷地やより高い快適性を求める方には物足りない可能性があります。
断熱等級5は、冬の室温が10℃を下回らない程度が目安で、2030年には新築の最低基準になる予定です。
温暖な地域では快適な場合も多いですが、将来の基準を見据えると、より上位の等級6を検討する価値は十分にあります。
注文住宅の性能に関連する他の記事
ZEH(ゼッチ)とは?今さら聞けない基本をわかりやすく解説!
これから家を建てるなら必須!「長期優良住宅」のメリットと申請方法を解説
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。
あわせて読みたい
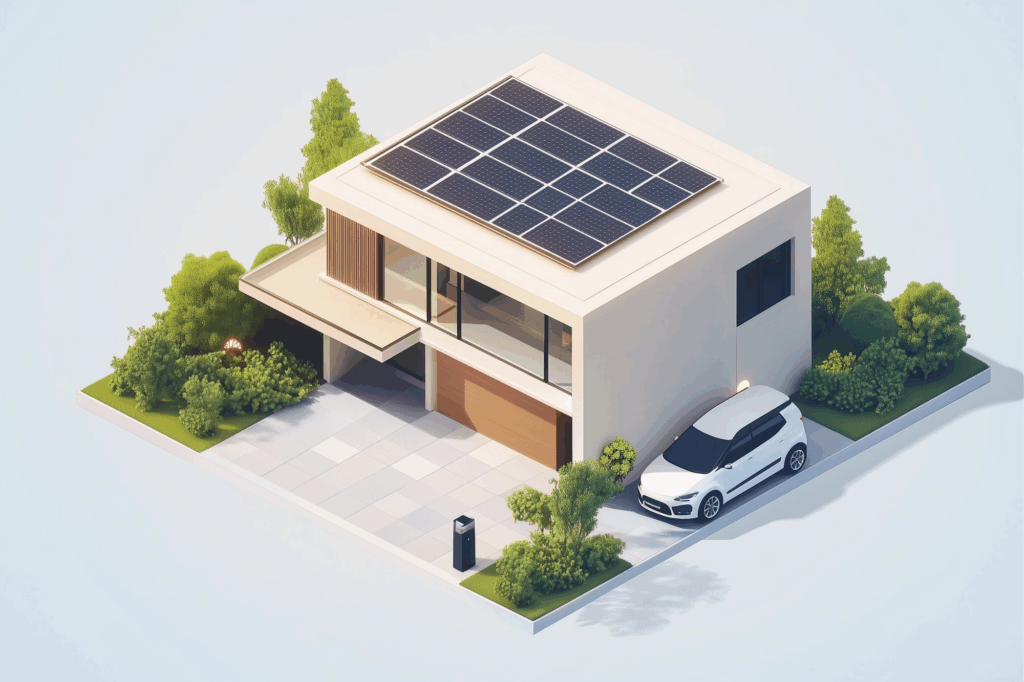
家づくりのはなし
高性能住宅って何?特徴やメリットをわかりやすく解説!








![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)


