
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。
注文住宅は「理想の家」を建てられる一方で、土地選びを誤ると大きな後悔につながります。
日当たりや周辺環境、法的規制など見落としがちなポイントも多く、入居後に気づくケースも少なくありません。
ここでは、後悔した事例や注意すべきポイントをご紹介します。
注文住宅の土地選びの難しさとは?
注文住宅を建てる際、土地選びは最も重要であると同時に、最も難しいステップのひとつです。
希望するマイホームを実現するためには、土地の広さや価格、場所、周辺環境などを総合的に考慮しなければなりません。
土地選びを難しくしている要素のひとつは、「すぐに判断する必要がある」という点です。
人気のエリアや条件の良い土地は、すぐに他の購入希望者が現れるため、ゆっくり検討する時間がないことが多いのです。
このような状況下で焦って決定を下すと、後々失敗を招く可能性が高まります。
▼関連記事
注文住宅の土地探しはどうすればいい?コツや注意点、流れを紹介!
土地探しはどこに相談しに行けばいい?ハウスメーカー?不動産会社?コツや注意点も解説
【注文住宅】土地探しの優先順位はどう決める?条件やポイントを紹介!
注文住宅の土地選びの失敗事例と対策

土地選びは家づくりの第一歩ですが、見落としから思わぬ失敗に繋がることもあります。
ここでは土地選びの事例とその対策をご紹介します。
【失敗事例1】土地に予算をかけすぎ、建物が簡素になった
土地の価格だけで予算を組んでしまい、後からかかる諸費用を考慮していなかったため、総予算が大幅にオーバー。
その結果、建物本体の費用を削らざるを得ず、希望の間取りや設備を諦めることになった。
【対策】総予算から考え、土地と建物のバランスを意識する
まず「土地+建物+諸費用」の総予算を明確にしましょう。
土地購入には、仲介手数料、登記費用、不動産取得税などの諸費用がかかります。
一般的に、土地価格の5〜10%程度が諸費用の目安とされています。
さらに、地盤が弱い土地の場合は地盤改良工事に、上下水道が引き込まれていない場合は引き込み工事に別途費用が発生することもあります。
【失敗事例2】理想の家が建てられない土地だった
購入した土地が、建ぺい率や容積率、斜線制限などの法規制により、想定していた大きさや高さの家を建てられないことが判明した。
【対策】購入前に建築のプロに相談し、法規制を確認する
土地には、都市計画法や建築基準法に基づき、建てられる建物の大きさを制限する「建ぺい率」(敷地面積に対する建築面積の割合)や「容積率」(敷地面積に対する延床面積の割合)が定められています。
これらの規制を超えた建物は建築できません。
気になる土地が見つかったら、契約前にハウスメーカーや工務店の担当者に相談し、希望の間取りが入るかどうかの簡易的なプラン(ボリュームチェック)を依頼しましょう。
【失敗事例3】周辺環境の確認が不十分で、住んでから後悔した
昼間の下見では静かで良い場所だと思ったが、実際に住んでみると夜間の交通量が多くて騒がしかったり、近隣の工場からの臭いが気になったりした。
【対策】時間帯や曜日を変えて、何度も現地を訪れる
土地の周辺環境は、時間帯や曜日によって大きく変わることがあります。
昼間だけでなく、朝の通勤時間帯、夜間、そして平日と休日、それぞれの状況を確認することが重要です。
また、自分の足で周辺を歩き、駅やスーパー、学校までの実際の距離や道のりの安全性(坂道の有無、街灯の数など)を確認することも、住んでからの「こんなはずじゃなかった」を防ぐために不可欠です。
【失敗事例4】インフラ未整備で、高額な追加工事費が発生した
安価な土地だと思って購入したら、上下水道管やガス管が土地の前面道路まで引き込まれておらず、その引き込み工事に数百万円の追加費用がかかってしまった。
【対策】上下水道・ガスなどのインフラ状況を事前に確認する
特に郊外や古い住宅地の土地を検討する際は、水道・下水・ガスといったライフラインの整備状況を必ず確認しましょう。
住宅会社や不動産会社への確認はもちろん、市役所の担当部署で前面道路の配管状況を教えてもらうこともできます。
もし引き込み工事が必要な場合は、事前に概算費用を把握しておくことが大切です。
【失敗事例5】災害リスクの高い土地だと知らなかった
購入後に、その土地が洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に指定されていることを知った。
地盤が軟弱で、地震の際の液状化リスクが高いエリアだった。
【対策】ハザードマップを確認し、土地の安全性を調べる
マイホームを建てる土地の安全性は最も重要なポイントの一つです。
国土交通省や各自治体が公開しているハザードマップポータルサイトなどを活用し、洪水、土砂災害、津波などの災害リスクを必ず確認しましょう。
また、昔の地名や古地図から、その土地がもともと川や沼地、田んぼでなかったかを調べることも地盤の強さを推測する手がかりになります。
土地選びをする際に気を付けることとは?

土地を選ぶ際には、不適切な選択をすると後々大きな後悔を招く可能性があります。
そのため、失敗を避けるための注意点をしっかり把握しておきましょう。
ここでは、特に気を付けるべき土地の特徴について詳しく解説します。
厳しい制約がある土地
建築基準法による制約が特に厳しい土地を購入すると、理想の住まいが建てられない可能性があります。
たとえば、高さ制限や建ぺい率・容積率が厳しい土地、または接道義務を満たしていない土地などは要注意です。
このような土地だと、間取りを自由に設計することが難しくなり、注文住宅でありながら妥協せざるを得ない場面が増えてしまいます。
造成・工事に「追加費用」がかかる土地
造成工事が必要な土地や地盤の強化が必要な土地は、建築費用とは別に大きな追加費用がかかる場合があります。
また、水道やガスなどのインフラが整備されていない土地では、ライフラインを整えるために高額な工事費が発生することもあります。
このようなケースでは、表面上の土地価格が安く見えても、結果的に全体として高額な出費となり、後悔につながる可能性があります。
災害リスクの高い土地
ハザードマップで確認せずに土地を購入した場合、災害リスクの高い地域であることに後から気づき、後悔することがあります。
特に浸水リスクや地震、土砂災害の発生可能性が高い土地は、住んだ後の安全性に直接関わります。
たとえば、河川の近くや急斜面が隣接する土地、軟弱な地盤の土地などは特に注意が必要です。
日当たりの悪い土地
日当たりが悪い土地を選んでしまうと、家の中が暗くなりがちで、長期的に居住する際の快適さを損なう場合があります。
特に北向きの土地や周囲を高い建物で囲まれている土地では、十分な採光が確保できず、生活の質を下げてしまうことがあります。
土地選びで大切なこととは?
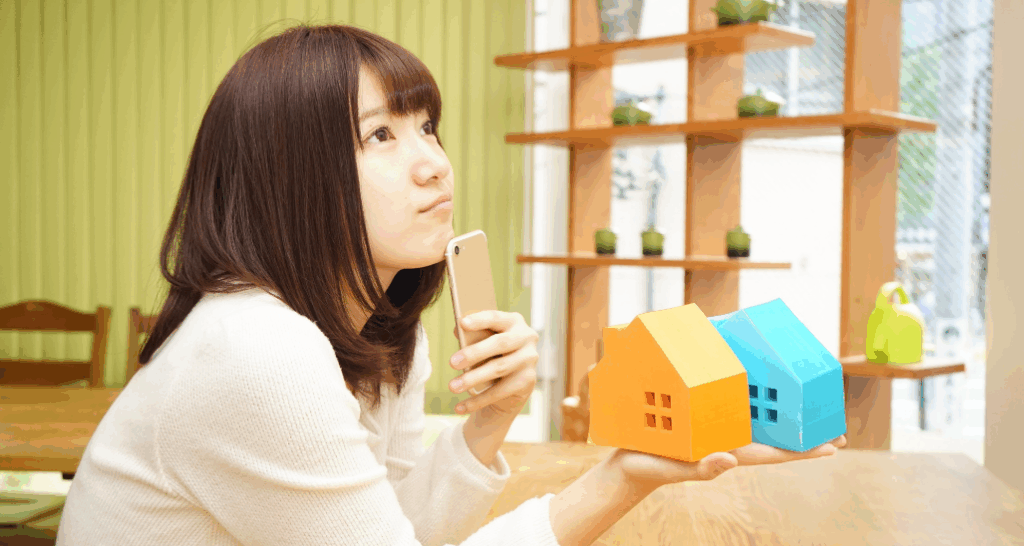
注文住宅の土地選びは、まず総予算から建物代と諸費用を引いて、土地にかけられる費用を明確にすることが重要です。
土地の安さだけで選ぶと、法規制や地盤改良などで希望の家が建てられなかったり、高額な追加費用が発生したりする恐れがあります。
こうした失敗を防ぐため、建築のプロである住宅会社と早い段階から一緒に土地探しを進めるのが成功の鍵です。
専門的な視点で、希望のプランが実現可能か、土地に隠れたリスクはないかを判断してもらえます。時間帯を変えて現地を訪れ、周辺環境や災害リスクを確認することも欠かせません。
注文住宅の土地選びに関するよくある質問
注文住宅の土地選びでは、やめた方がいい土地や縁起など多くの疑問が生まれます。
ここでは、土地探しでよくある質問を取り上げ、回答します。
やめたほうがいい土地の特徴は?
以下のような土地が挙げられます。
・ハザードマップで災害リスクが高い土地
・騒音・振動・排気ガスがひどい土地
・日当たりや風通しが極端に悪い土地
・悪臭や騒音などが懸念される施設が近い土地
・隣地との境界が曖昧な土地
・前面道路が極端に狭い土地
買うべきではない土地は?
境界線が曖昧で隣地所有者とトラブルになるリスクがある場合やインフラ整備が不十分な土地が挙げられます。
土地選びの段階でこれらの要素を見逃すと後悔に繋がるため、物件の条件を細かくチェックすることが重要です。
どんな土地が縁起が悪いですか?
T字路の突き当たりや三角形の土地は、悪い気を直接受けるため凶相とされます。
また、墓地や井戸、沼地の跡地などは陰の気が強いとされ、運気を下げると考えられています。
土地の形状や過去の用途が、縁起の良し悪しに影響すると言われます。
高い土地(高台)に住む良さは何ですか?
眺望の良さがあります。
高台の土地の場合、広々とした景色や夜景を楽しむことができ、日々の暮らしが豊かになると好まれるケースが多いです。
また、水害リスクが低い点も大きな魅力です。
土地に関連する記事
「建ぺい率」と「容積率」とは?わかりやく基礎知識や緩和条件を解説!
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。








![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)


