
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。
プライベートな空間で光や風を感じられる「中庭のある家」。注文住宅で人気ですが、知っておくべきデメリットも。この記事では、後悔しないためにメリット・デメリットや間取りのアイデアを解説します。
中庭のある家とは?
中庭のある家とは、建物の内側に塀や建物で囲まれた屋外の庭を設けた住宅のことを指します。また、「コートハウス」と呼ばれることもあります。
近年、注文住宅の間取りの選択肢として、中庭のある家が非常に注目されています。このタイプの住宅は、都会の狭小地や周囲が建物に囲まれたエリアでも、プライバシーを確保しながら快適な屋外空間を楽しむことが可能です。中庭は、暮らしを豊かにし、採光や通風を確保するだけでなく、おしゃれな空間デザインの一部としても活用されています。
現代住宅で中庭が注目される理由
中庭が現代の家づくりで注目されている理由の一つは、住環境が変化しているためです。
都市部では隣家との距離が近い場合も多く、外からの視線やプライバシーに配慮する必要がありますが、中庭のある家ならその心配を軽減できます。
また、自然光を家全体に行き渡らせることができ、光を取り込むことで明るく快適な空間を実現できます。
中庭のある家は、現代的な注文住宅の中で機能性とデザイン性を両立させた間取りのアイデアとして注目されているのです。
中庭の形状について(口の字型・コの字型・L字型)

中庭の形状は一般的に3つの種類があります。
ここでは3つの形状について説明します。
口の字型
建物の真ん中に庭を配置し、四方を完全に囲む「ロの字型」は、最もプライベート性が高い究極の中庭スタイルです。
外部からの視線を完全にシャットアウトできるため、カーテンを開け放った開放的な暮らしが実現します。
どの部屋からも中庭の緑や光を感じられるのが魅力ですが、建築コストは高くなる傾向にあり、雨水の排水計画や、熱気がこもらないための通風計画をしっかり行うことが、快適な住まいにするための重要な鍵となります。
コの字型
三方を建物で囲み、一方向だけが開いている「コの字型」は、プライバシーと開放感のバランスに優れた人気のスタイルです。
外部からの視線を適度に遮りつつ、ロの字型のような完全な閉塞感がないため、光や風をより多く取り込むことができます。
リビングとダイニングで中庭を挟むなど、空間に繋がりと奥行きが生まれるのも魅力です。
ただし、開けている方角によっては、隣家からの視線や日当たりを考慮した設計の工夫が求められます。
L字型
建物をL字に配置し、その内側に庭を設ける「L字型」は、比較的コストを抑えながら中庭のある暮らしを実現できる、現実的なスタイルです。
角地や変形地にも柔軟に対応しやすく、ウッドデッキなどを設ければリビングと一体化した開放的な空間を手軽に作れます。
ロの字型やコの字型に比べて開放的である分、道路や隣家からの視線が入りやすいため、フェンスや植栽を効果的に活用し、プライバシーを確保する外構計画が重要になります。
中庭のある家のメリット

プライバシーと快適な屋外空間
中庭のある家は外部からの視線を遮りながらも、家の内側に快適な屋外空間を作り出せるのが大きなメリットです。
特に近隣の視線を気にせず、安心してくつろげるプライベートなスペースとして活用できます。
中庭ではバーベキューや読書、日向ぼっこなどが楽しめるため、家族全員が安心して過ごせる空間となります。
採光と通風性の向上
中庭のある家では、建物の中央部分に空間があるため、周囲の部屋に自然光を取り入れやすくなります。
また、間取りによっては風通しも良くなり、夏場でも快適に過ごせる家が実現します。
「中庭」という開放的な空間があることで、家全体の表面積が増え、光や風を効果的に取り込むことが可能になります。
家族の憩いの場としての役割
中庭は家族や友人が自然と集まる憩いの場として、コミュニケーションの中心にもなり得ます。
特に小さなお子さまがいるご家庭では、親の目が届く範囲で安心して遊ばせることができるため、非常に役立ちます。
また、ペットを飼っている場合も中庭を安全な遊び場として活用できます。家族の中で日常的に共有できるスペースがあることで、暮らしの質がぐっと向上するでしょう。
室内外を繋ぐデザイン性
中庭は建物の一部でありながら、屋外の開放感を兼ね備えているため、室内と屋外の境界線を柔らかくつなぐデザイン性が特徴的です。
リビングやダイニングに続く形で中庭を設計することで、視覚的に広がりのある空間を演出できます。
また、「注文住宅」で中庭を取り入れる際には、素材や植物の選び方を工夫することでさらに魅力的な空間を作ることができます。
このようなデザイン性の高さは、機能性だけでなく家そのものの価値を引き上げる要素としても注目されています。
中庭のある家のデメリット
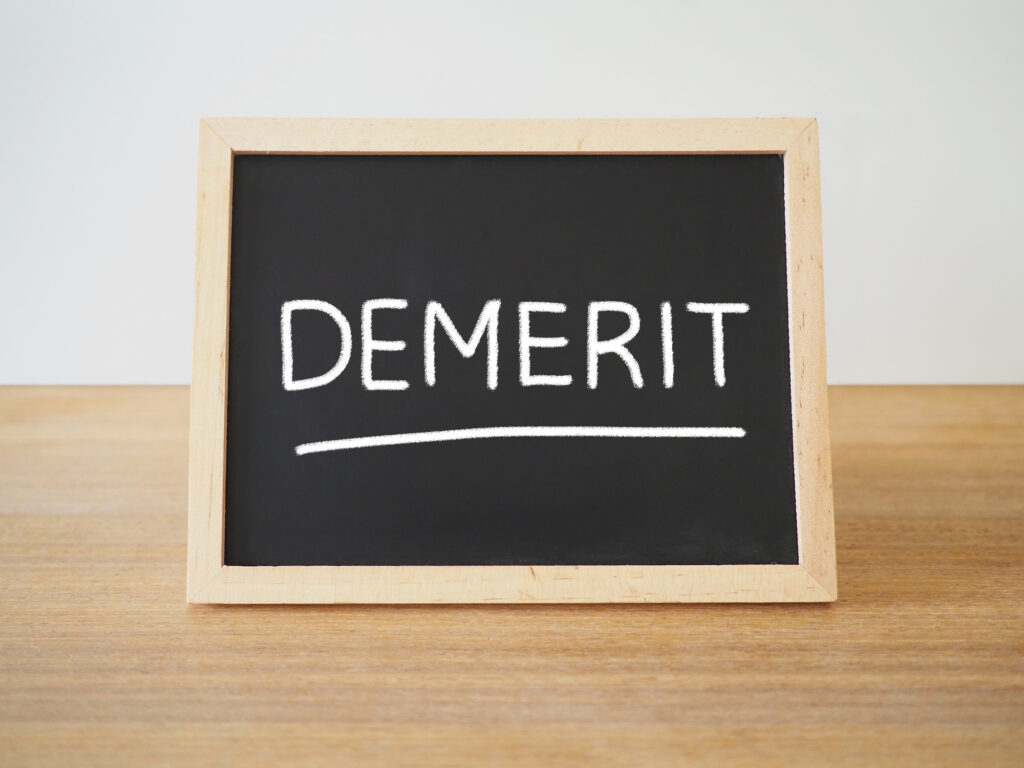
建築コストとメンテナンスの負担
中庭のある家はその独特な設計から、建築コストが一般的な住宅に比べて高くなりがちです。
たとえば、コの字型やロの字型の間取りは壁面や窓が多くなるため施工が複雑になり、結果として費用が増加します。
また、中庭そのものの維持管理にも注意が必要です。植物の手入れや掃除、排水設備のメンテナンスなど、日常的に手間がかかることも「中庭のある家」のデメリットとして挙げられます。
設計・施工時に発生する制約
中庭のある家は、間取りや構造が特定の形状に依存するため、設計や施工の自由度が制限される場合があります。
たとえば、敷地の広さや形状によっては理想の中庭を作ることが難しいことがあります。
また、隣家との距離や日照条件も設計に影響を与えるため、十分な計画が求められます。
これらの制約を無視することは、後悔につながりやすいため、注文住宅の計画段階で綿密な検討が欠かせません。
生活動線に影響が出ることも
中庭を取り入れた間取りは、生活動線に影響を及ぼすケースもあります。
ロの字型やコの字型の家では、中庭を囲むように各部屋が配置されることが多いため、移動の際に中庭をぐるりと回る必要があります。
これにより、利便性が低下したり、日常の家事や暮らしに不便を感じる場合もあるでしょう。
冷暖房の効率に影響
中庭を設けることで、家全体の空調効率が低下する可能性があります。
中庭は建物内に大きな開放空間を生むため、外気の影響を受けやすくなります。
特に夏場は日差しが強く、冬場は冷気が侵入しやすいことがデメリットとなり、冷暖房費の増加を招くこともあります。
このような問題を回避するためには、中庭周辺の断熱性能を高めたり、庇(ひさし)や植栽を上手く活用して気候調整を行う工夫が必要です。
中庭のある家で後悔しないためのポイント

「何のための中庭か」と「どう掃除するか」を最初に決める
中庭を成功させる鍵は、利用目的の具体化と維持計画です。
子どもの遊び場、バーベキュースペースなど、目的によって床材や必要な水道・コンセント設備が決まります。
目的が曖昧だと、ただの活用されない空間になりがちです。
また、中庭は屋外であり、落ち葉や砂埃で必ず汚れます。
誰がどう掃除するのか、詰まりにくく掃除しやすい排水口を設けること、掃除道具の収納場所まで、設計段階で現実的に計画しておくことが後悔を防ぎます。
「夏の日差し」と「大雨」への対策
中庭は夏の日差しで高温になりやすく、室温上昇の原因にもなります。
照り返しで使えなくなる事態を防ぐため、シェードやオーニングの設置準備、深い軒の設計、遮熱・断熱性の高い窓ガラスの採用が不可欠です。
また、ゲリラ豪雨による浸水リスクにも備えなければなりません。
十分な排水能力を持つ排水口を複数設け、床に適切な水勾配をつける設計が命綱です。定期的な排水口の掃除も欠かせません。
「見るだけ」でなく「使える」ようにする
中庭を鑑賞用で終わらせないためには、室内との一体感が重要です。
リビングと床の高さを揃えて段差をなくし、扉を全て引き込める全開口サッシなどを採用すると、中庭が「部屋の延長」として気軽に使えるようになります。
さらに、ガーデニングや掃除、食事に活躍する水道・屋外コンセント、夜の雰囲気を楽しむ照明といった設備は、活用の幅を大きく広げます。
これらは中庭を「使う」ための必須装備と考えるべきです。
「外からの視線」と「音の響き」を想定
壁に囲まれていてもプライバシーが完璧とは限りません。
隣家の2階など、上からの視線を遮る壁の高さや屋根の計画が重要です。
道路に面する場合は、格子や植栽で視線をコントロールしましょう。
また、中庭は音が反響しやすく、子どもの声や会話が騒音になりがちです。
ウッドデッキや植栽で音を吸収させ、窓の防音性を高めるなどの対策が必要です。
自分たちのプライバシーを守り、ご近所への配慮を忘れないことが大切です。
おしゃれな中庭のある家にするアイデア
最後に、おしゃれな中庭のある家にするためのアイデアを3つご紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
リビングの床と「高さ」と「素材感」を揃える
中庭をおしゃれに見せる最も効果的な方法の一つが、リビングとの一体感を演出することです。
ポイントは、リビングの床と中庭のウッドデッキやタイルの「高さ」を完全にフラットに揃えることです。
室内と屋外を隔てる段差をなくすだけで、視線がスムーズに外へと抜け、空間に驚くほどの広がりと開放感が生まれます。
さらに、床材の「素材感」を意識して近づけることで、その効果は格段に高まります。
たとえば、リビングのフローリングと色調や木目を合わせたウッドデッキを選ぶ、モダンな内装なら同じトーンのタイルで統一するなど、視覚的な連続性を持たせましょう。
これにより中庭は、気軽に使える「もう一つのリビング」となり、家全体が洗練された統一感のある空間に仕上がります。
手のかからない「シンボルツリー」を1本だけ植える
「緑のある暮らしに憧れるけれど、手入れはできるだけ避けたい」そんな方に最適なのが、厳選した「シンボルツリーを1本だけ」植えるというアイデアです。
あえて植栽を1本に絞ることで、その木の持つ美しい樹形や葉の表情が際立ち、空間全体の主役としてフォーカスされます。
これにより、ごちゃごちゃした印象にならず、すっきりと洗練された「引き算の美学」が生まれるのです。
重要なのは、成長が緩やかで病害虫にも強い、手のかからない樹種を選ぶことです。
アオダモやソヨゴ、ハイノキなどは人気の選択肢です。窓からふと見える一本の木が、季節の移ろいを教えてくれ、日々の暮らしに豊かな彩りと癒やしを与えてくれるでしょう。
「光と影」を操るナイトライティング
夜の中庭は、照明計画一つで昼間とは全く異なる表情を持つ、上質で特別な空間に生まれ変わります。
ここでのポイントは、全体をただ明るく照らすのではなく、「光と影」を巧みに操り、ドラマチックな陰影を生み出すことです。
たとえば、シンボルツリーや特徴的な壁を下からアッパーライトで照らせば、その立体感が際立ち、壁に映る影はまるでアートのように幻想的な雰囲気を醸し出します。
また、足元を優しく照らすフットライトは、安全性を確保しながら落ち着いた大人の空間を演出するのに最適です。
夜風にあたりながら過ごす時間が格別なものになるだけでなく、防犯効果も高まります。省エネなLED照明を選び、設計段階で配線計画をしっかり行いましょう。
中庭の関連記事
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。








![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)


