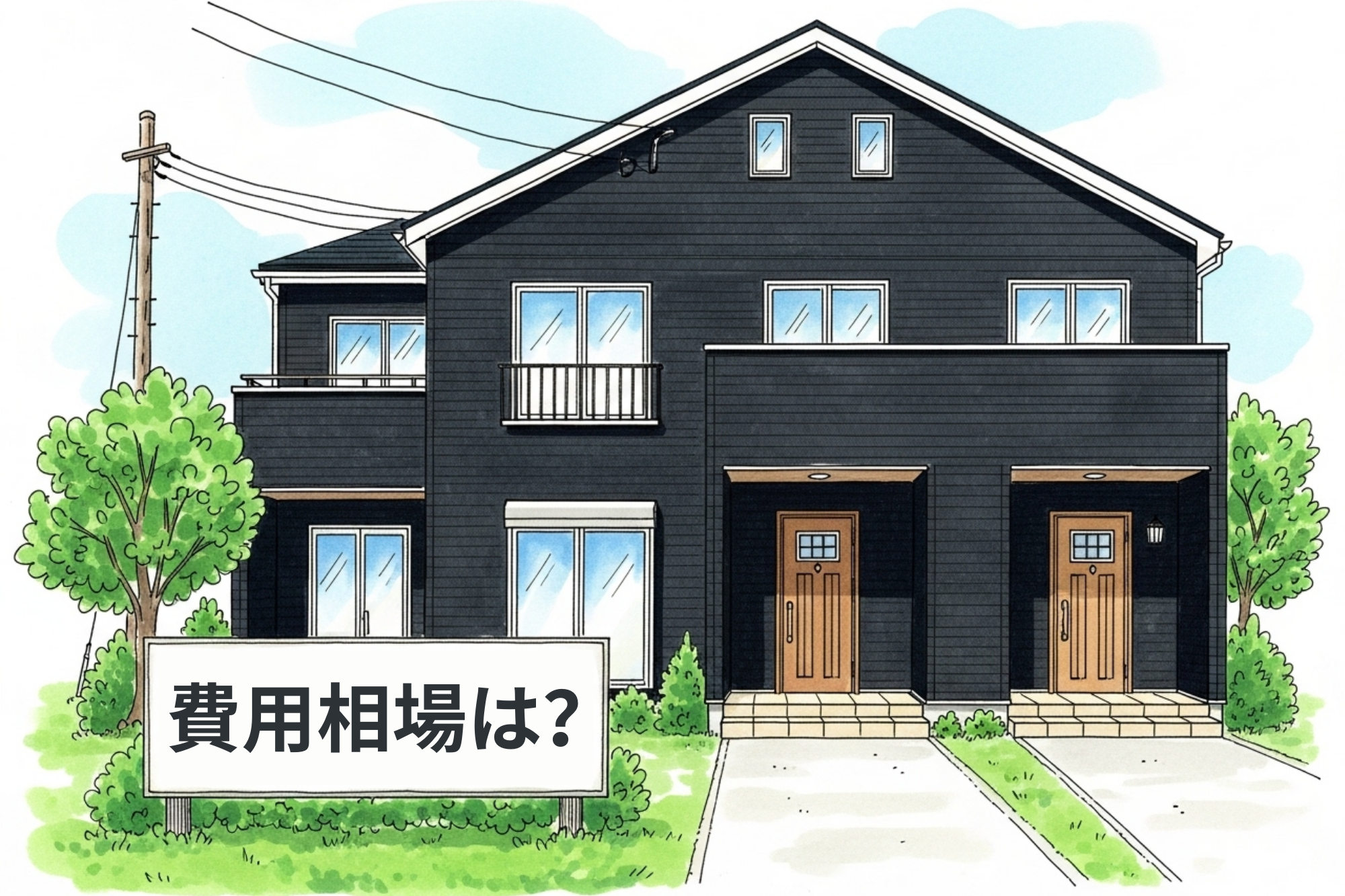
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。
親子で暮らす二世帯住宅。
でも一番気になるのは「一体いくらかかるの?」というお金のことですよね。
この記事では、完全分離型・部分共有型といったタイプ別のリアルな費用相場から、建築費の内訳、賢くコストを抑えるポイントまでを解説します。
後悔しない資金計画の第一歩に、ぜひお役立てください。
【土地代+建物代】二世帯住宅の総額の目安
土地代と建物代を合わせた二世帯住宅の総額は、およそ5,000万円〜1億円以上が一般的な目安となります。
ただし、これは土地の価格によって大きく変動します。
以下に、その内訳となる「広さ」と「相場」の目安を解説します。
■ 建物の広さと価格の目安
一般的な広さ(延床面積):50坪〜70坪 (約165㎡〜231㎡)
二世帯が暮らすため、一般的な単世帯住宅(30〜40坪)より広いスペースが必要になります。
建物の価格相場:3,500万円〜6,000万円
完全分離型か部分共有型か、また設備のグレードによって価格は変動します。設備の多い完全分離型は高くなる傾向にあります。
■ 土地の広さと価格の目安
必要な広さ(敷地面積):60坪〜80坪 (約200㎡〜265㎡)
大きめの建物に加え、各世帯の車を置く駐車スペース(2〜4台)を確保するために、ある程度の広さが必要になります。
土地の価格相場:1,500万円〜5,000万円以上
土地代はエリアによって最も価格差が出る部分です。地方や郊外であれば1,000万円台から探せますが、首都圏などの都市部では5,000万円以上になることも珍しくありません。
※あくまで目安になるので、必ずこの費用がかかるわけではありません。
【注文住宅】二世帯住宅のタイプ別費用相場

注文住宅で建てる二世帯住宅の3つのタイプ別に、建物の建築費(本体工事費)の相場を解説します。
※あくまで目安です。
※土地代や外構工事費、諸費用は含みません。
※延床面積60坪(約200㎡)の家を建てる場合をモデルケースとします。
完全共有型の二世帯住宅の相場
完全同居型:3,600万円~5,400万円
玄関・キッチン・浴室・リビングなど、ほとんどの設備や空間を共有するタイプです。
基本的には「大きな一つの家」となるため、坪単価は一般的な単世帯住宅と大きく変わりません。
3つのタイプの中では最も建築費を抑えることができます。
特徴: 建築費は安いが、プライバシーの確保が課題。
坪単価の目安: 60万円~90万円
一部共有型の二世帯住宅の相場
部分共有型:4,200万円~6,000万円
玄関や浴室など一部を共有しつつ、キッチンやリビング、トイレなどは各世帯に設けるタイプです。
どこを共有するかによって費用は大きく変動しますが、設備の数が増える分、完全同居型よりはコストが上がります。
プライバシーと費用のバランスが取りやすいのが特徴です。
特徴: 費用とプライバシーのバランス型。共有範囲がコストを左右する。
坪単価の目安: 70万円~100万円
完全分離型の二世帯住宅の相場
完全分離型:4,800万円~7,200万円以上
玄関から水回り、居住空間まで、すべてを完全に世帯ごとで分けるタイプです。
設備が2つずつ必要になり、壁や床の構造も複雑になるため、建築費は最も高額になります。
税制上の優遇措置を受けやすいというメリットもあります。
特徴: プライバシーは最大限確保できるが、費用は最も高くなる。
坪単価の目安: 80万円~120万円
二世帯住宅にかかる費用の内訳は?

二世帯住宅を建築する際には、建築費用の内訳をしっかりと把握することが重要です。
一般的には「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つに分類されます。
これらを理解することで、どの部分にどのくらい費用がかかるのか明確にし、効率的に予算を組むことができます。
本体工事費
本体工事費は、総費用の約70~80%を占めることが多くみられます。
建物そのものを建てるための費用で、見積もりの中で最も大きな割合を占めます。
具体的には、基礎工事、柱や梁などの構造躯体、屋根、外壁、内装(床・壁・天井)、窓やドア、キッチン・浴室・トイレといった住宅設備の費用などが含まれます。
付帯工事費
付帯工事費は、総費用の約15~20%を占めることが多くみられます。
建物本体以外で、その土地に住めるようにするために必要な工事費用全般を指します。
たとえば、古い家の解体費用、地盤が弱い場合の改良工事費、水道・ガス・電気の引き込み工事、駐車場や門、フェンスなどの外構工事費などがこれにあたります。
土地の条件によって費用が大きく変動するため、あらかじめ確認が必要です。
諸費用
諸費用は、総費用の約5~10%を占めることが多く見られます。
工事以外で発生する手数料や税金などの費用です。
住宅ローンの手数料や保証料、建物の登記費用、不動産取得税、火災保険料、契約書に貼る印紙税などが含まれます。
これらは基本的に現金での支払いが必要になることが多いため、建築費用とは別に自己資金として準備しておく必要があります。
二世帯住宅の費用を左右する要因は?
二世帯住宅の費用を最も大きく左右するのは、玄関や水回りをどこまで分けるかという「分離度」です。
設備が2つずつ必要になる完全分離型が最も高額になります。
次に、当然ながら建物の「延床面積(広さ)」が大きくなるほど費用は上がります。
また、キッチンや浴室などの「設備のグレード」、断熱性や耐震性といった「住宅性能」も価格に直結します。
さらに、凹凸の多い複雑な形状より、シンプルな箱型の「建物の形状」にする方がコストを抑えられます。これらの要因の組み合わせで総額が大きく変動します。
注文住宅の二世帯住宅で費用を抑えるポイント

費用を左右する要因は様々ですが、計画段階の工夫でコストを抑えることは可能です。
ここでは、予算内で理想の二世帯住宅を実現するために、費用を抑えるポイントを4つご紹介します。
共有部分を増やし、分離度を下げる
二世帯住宅で費用を抑えるポイントの一つは、共有部分を増やし、建物の分離度を下げることです。
たとえば、玄関やリビング、キッチン、浴室などを完全に分離させるのではなく、一部を共有する設計にすることで、建築コストを大幅に抑えることができます。
特に完全同居型や一部共有型の二世帯住宅は、必要な設備が完全分離型よりも少なくなるため、二世帯住宅の相場としても比較的低価格で済むことが多いです。
建物の形を凹凸の少ない総二階にする
建築費用を抑えるためには、建物の形状にも工夫を加えることが有効です。
凹凸が多い複雑な形状の住宅は、材料費や施工費が増加するため、費用面で負担が大きくなります。
一方で、シンプルな総二階のデザインはコストを抑える効果が大きいです。
総二階建ての構造は、基礎工事と屋根工事の面積を最小限にすることが可能で、コストパフォーマンスに優れています。
この方法は、二世帯住宅の相場を考える際に非常に有効な選択肢と言えるでしょう。
設備や内装のグレードにメリハリをつける
設備や内装の選択にメリハリをつけることも、費用を抑えるための重要なポイントです。
二世帯住宅を注文住宅で考える際、すべてのスペースに高級素材を使用するのではなく、使用頻度の高い箇所にはグレードの高い設備を取り入れ、それ以外の箇所ではコストを抑えた素材や設備を選ぶと効果的です。
たとえば、キッチンや浴室の設備にはある程度の費用をかけ、寝室や廊下などにはコストを抑えた内装を使用することで、無理のない価格設定が可能となります。
廊下を減らすなど、延床面積をコンパクトにする
延床面積をコンパクトにすることも、二世帯住宅の建築費を抑えるポイントです。
広い住宅は快適さがありますが、建築費用が増加します。
そのため、動線の工夫により廊下を減らしたり、使わないスペースを最小限に設計することで、建物全体の面積を抑えることができます。
また、共有部分を増やすことで、重複するスペースを省き、効率的な設計へと繋げることが可能です。
延床面積を意識して設計することで、注文住宅の二世帯住宅相場以内に収めやすい建物計画が実現します。
二世帯住宅に関するよくある質問
二世帯住宅の平均金額は?
結論から言うと、建物の建築費用だけで見ると平均3,500万円〜5,000万円、土地も一緒に購入する場合は総額で5,000万円〜7,000万円がひとつの目安です。
これはあくまで全国平均の目安であり、実際には家の広さや分離タイプ(完全分離か部分共有か)、建築するエリア(特に土地代)によって大きく変動します。
住宅金融支援機構の2022年度の調査によると、注文住宅の全国平均建築費は約3,715万円でした。
二世帯住宅はこれよりも広く、設備も多くなるため、建築費は高くなる傾向にあります。
二世帯住宅は誰が払うのですか?
二世帯住宅の費用負担については、事前に親世帯と子世帯の間でしっかり話し合いをしておくことが重要です。
一般的には、親世帯が土地を所有し、建築費用は子世帯が主に負担するケースが見られますが、双方で建築費用を折半する場合や、親世帯が全額負担する場合もあります。
二世帯住宅にして良かったことは何ですか?
二世帯住宅にして良かった点として挙げられるのは、親世帯と子世帯が協力しやすい生活環境が作れることです。
たとえば、親世帯が子育てを手伝うことで、小さな子どもがいる家庭は安心して仕事に専念できるでしょう。
「二世帯住宅」に関連する記事
二世帯住宅は完全分離型がいい?建築費用の目安やメリット、デメリットを解説!
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。








![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)


