
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。
プライバシーを保ちつつ、ほどよい距離感で暮らせる「完全分離型の二世帯住宅」。
理想の暮らしを夢見て建てたものの、「こんなはずでは…」と後悔するケースは少なくありません。
この記事では、後悔の具体例を交えながら、理想の二世帯住宅を実現するために知っておきたい重要なコツを徹底解説します。
二世帯住宅の完全分離型は本当に後悔する?
結論から言うと、完全分離型の二世帯住宅は必ず後悔するわけではありません。
しかし、理想と現実のギャップから後悔につながるケースが多いのも事実です。
各世帯のプライバシーを最大限尊重できるという大きなメリットがある一方で、その独立性がかえって建築費や光熱費といった金銭問題、生活音トラブル、将来の介護や空き家問題などを引き起こす火種にもなり得ます。
「こんなはずではなかった」とならないためには、メリットだけに目を向けず、起こりうるデメリットを理解し対策を講じることが何より重要です。
▼関連記事
二世帯住宅は完全分離型がいい?建築費用の目安やメリット、デメリットを解説!
二世帯住宅がデメリットだらけと言われている理由とは?失敗しないための対策も紹介!
二世帯住宅の完全分離型で後悔した事例

理想の暮らしのはずが、現実は甘くありませんでした。
ここでは、完全分離型の二世帯住宅で起こった、6つの具体的な後悔の事例をご紹介します。
金銭面から人間関係のトラブルまで、リアルな声に耳を傾けてみましょう。
「基本料金が倍なんて…」想定外の光熱費で家計が火の車に
◾️後悔事例①
「プライバシーを守りたかったので、光熱費のメーターも全て別にしました。建築会社からは『使った分だけの支払いで公平ですよ』と言われ納得していたのですが、実際に暮らし始めると電気・ガス・水道すべての基本料金が二重にかかり、予想より毎月1万円以上も出費が増えてしまいました。共働きの私たちと、日中家にいることが多い両親とでは電気の使用量も違い、負担の公平さを求めたはずが、かえって家計を圧迫する結果になり後悔しています。」
◾️解説
完全分離型では、各世帯で光熱費の契約を結ぶため、基本料金がそれぞれ発生します。
これを見落とすと、毎月のランニングコストが想定を上回る可能性があります。
あらかじめ光熱費のシミュレーションを行い、共有メーターで費用を按分する方法も比較検討するなど、長期的な視点で資金計画を立てることが重要です。
「孫の足音が筒抜け…」防音対策不足でギクシャクした関係に
◾️後悔事例②
「1階が親世帯、2階が私たち子世帯の完全分離型です。設計時に『最近の家は防音性が高い』と聞き、特別な対策はしませんでした。しかし、暮らし始めると子どもがリビングを走り回る音が想像以上に階下に響くらしく、親から『少し静かにしてくれないか』と苦情が。それ以来、子どもを叱る回数が増え、親世帯にも気を遣う毎日。せっかくのマイホームなのに、全く気が休まらない空間になってしまいました。」
◾️解説
完全分離型であっても、上下階の生活音は完全に遮断できるわけではありません。
特に子どもの足音のような重量衝撃音は響きやすい傾向にあります。
間取りを工夫し、水回りの位置を上下で揃えたり、寝室の上には居室を配置しないといった配慮が必要です。
また、床に防音材を入れる、二重床にするといった建築時の防音対策は、後からのリフォームが難しいため、設計段階で入念に検討することが後悔を防ぐ鍵となります。
「すぐ隣なのに遠い…」いざという時のサポートがしづらい
◾️後悔事例③
「将来の親の介護も考えて二世帯住宅にしました。玄関も別々の完全分離型ですが、ある夜、母が体調を崩したと父から電話が。慌てて様子を見に行こうにも、一度外に出て玄関のチャイムを鳴らさなければならず、数メートルの距離がとてももどかしく感じました。普段から顔を合わせる機会が少ないため、親の少しの変化にも気づきにくく、『何かあってからでは遅い』と、この距離感が不安になるときがあります。」
◾️解説
プライバシーを重視するあまり、コミュニケーションが希薄になりがちなのが完全分離型のデメリットの一つです。
玄関が別々だと、緊急時の行き来に手間がかかるだけでなく、日常的なサポートも心理的なハードルが上がりがちです。
完全に分離しつつも、室内で行き来できる内扉を設けるなど、緊急時や将来の介護を見据えた「つながり」を間取りに組み込んでおくことが大切です。
「親亡き後…」賃貸にも売却にも出せない巨大な空き家が負担に
◾️後悔事例④
「父が亡くなり、母も施設に入居したため、1階の親世帯スペースが完全に空いてしまいました。『完全分離型だから賃貸に出せる』と安易に考えていましたが、いざ募集すると『隣に大家さんが住んでいるのは気を遣う』と敬遠され、借り手が見つかりません。売却しようにも、二世帯住宅という特殊な間取りがネックで買い手がつかず、結局、使わない空間の固定資産税と維持費だけを払い続ける重荷になってしまいました。」
◾️解説
二世帯住宅は一般的な住宅に比べて需要が限られるため、売却が難しい傾向にあります。
特に完全分離型は建築コストが高い分、売却価格も高くなりがちです。
将来、親世帯のスペースが空くことを見越し、賃貸や売却を視野に入れるのであれば、地域の賃貸需要を調査したり、将来的に間取りを変更しやすい設計にしておくなどの対策が必要です。
「収納が足りない!」間取りの制約でどちらの世帯も不満
◾️後悔事例⑤
「限られた敷地に2つの玄関と2つのLDKを詰め込んだ結果、各部屋が狭くなり、特に収納スペースを大きく削ることになりました。暮らし始めると物が溢れかえり、片付けてもすぐに散らかってしまいます。お互いの世帯の希望を優先した結果、どちらの世帯にとっても中途半端で暮らしにくい間取りになってしまいました。もう少し収納を確保しておけば、と毎日後悔しています。」
◾️解説
一つの建物に二世帯分の居住機能を持たせるため、各世帯のスペースには制約が生まれがちです。
LDKや寝室の広さを優先するあまり、収納が不足するのはよくある失敗例です。
設計段階で、お互いの世帯の持ち物の量をしっかりと把握し、必要な収納量を確保することが重要です。
玄関を分けたことでシューズクロークが作れなかった、といった後悔も聞かれます。
「顔を合わせるのはゴミ出しの時だけ」コミュニケーションが希薄に
◾️後悔事例⑥
「お互いのプライバシーを尊重しようと完全分離型を選びました。その結果、生活時間が違うこともあり、親と顔を合わせるのは週に一度、ゴミ出しの時くらい。すぐ近くにいるのに、近所の人より会話が少ないかもしれません。先日、孫の誕生日会に誘うのさえ、電話でするような関係になってしまい、こんなことならもう少し交流が生まれる間取りにすればよかったと感じています。」
◾️解説
プライバシーの確保とコミュニケーションのバランスは、二世帯住宅の永遠の課題です。
完全分離型は、意識しないと世帯間の交流が全くなくなってしまう可能性があります。
たとえば、共有の庭やウッドデッキを設けて自然と顔を合わせる機会を作ったり、定期的に食事会を開くなどのルールを事前に話し合っておくことが、良好な関係を維持するために大切です。
二世帯住宅の完全分離型のメリット・デメリットまとめ
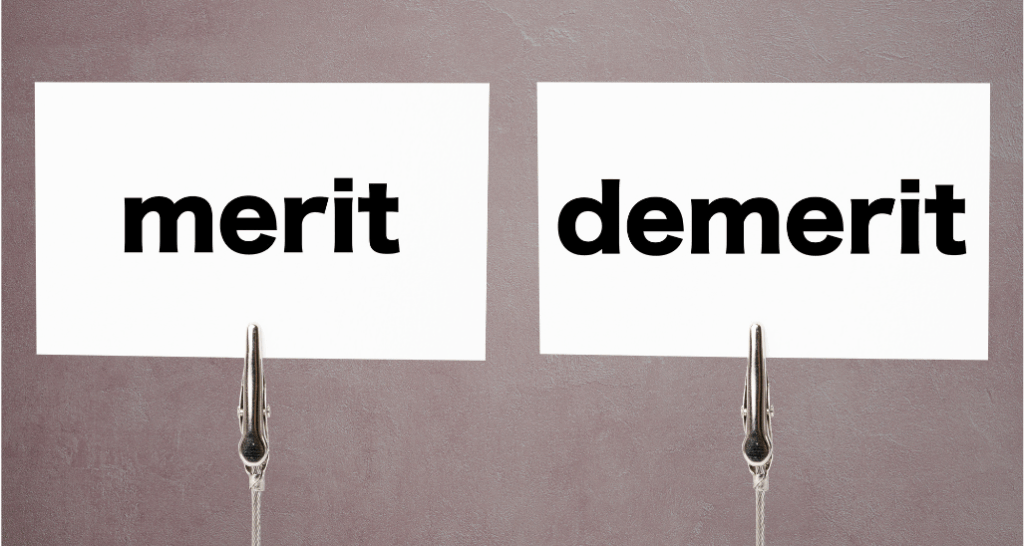
「プライバシー」という最大のメリットは、裏を返せば「コスト増」や「希薄な関係」というデメリットにもなります。
ここで改めて両面を整理し、メリットとデメリットを紹介します。
二世帯住宅の完全分離型のメリット
最大のメリットは、各世帯のプライバシーを最大限に確保できる点です。
対策をしていれば、基本的に生活音や生活時間のズレを気にすることなく、お互いのライフスタイルを尊重した暮らしが可能です。
また、キッチンや浴室といった水回りも各世帯で所有するため、気兼ねなく使うことができます。
光熱費のメーターを分ければ家計管理が明確になり、金銭的なトラブルを避けやすいのも利点です。
さらに、構造上「2戸の住宅」とみなされ、不動産取得税や固定資産税などの税制優遇を大きく受けられる可能性があります。
二世帯住宅の完全分離型のデメリット
最大のデメリットは、建築コストが高額になる点です。
玄関や水回りなど、ほぼ全ての設備が2つずつ必要になるため、一般的な住宅より広い土地と多くの費用がかかります。
また、暮らし始めてからも光熱費の基本料金が二重にかかり、月々の支出が想定以上になる可能性があります。
プライバシーが保たれる反面、世帯間のコミュニケーションが希薄になりやすく、いざという時の子育てや介護のサポートがしにくいという声も聞かれます
▼関連記事
二世帯住宅の完全分離で後悔しないためのコツ

これまで見てきた後悔事例は、事前の計画と少しの工夫で避けられるものがほとんどです。
ここでは、家族全員が笑顔で暮らすための、後悔しないための3つの重要なコツを解説します。
お金のルールを「契約書レベル」で明確にする
二世帯住宅の完全分離型は親世帯と子世帯が独立して暮らせるのが特徴ですが、光熱費や固定資産税など生活費の負担割合を曖昧にするとトラブルの原因になります。
電気・水道を別メーターにして使用分を精算するなど公平な仕組みを整え、口頭ではなく「契約書レベル」に明文化しておくことで、家族間でも安心して暮らせます。
「つながり」と「プライバシー」を両立する間取りを工夫する
完全分離型はプライバシーを守れる反面、「関係が希薄になった」という後悔も聞かれます。
そのため「適切な距離感」を保つ間取りの工夫が欠かせません。
たとえば、玄関は別でも室内で行き来できる共有スペースを設ければ、つながりと独立性のバランスが取れます。
また、お互いが快適に暮らすには音への配慮も重要です。
リビング同士が隣り合わないように設計したり、二重窓や防音ドアを採用したりするなど、建築段階での防音対策が後悔を防ぐ鍵となります。
10年後、20年後を見据えた「変化できる家」にする
注文住宅で二世帯住宅を建てるなら、10年、20年先の家族の変化を見据えた設計が後悔を防ぎます。
たとえば、親の高齢化を想定し、介護しやすい動線やバリアフリー設計をあらかじめ導入しておくと安心です。
また、親世帯が不在になった際に賃貸に出せるような間取りにしておけば、空き家リスクを資産活用に変えることも可能です。
このようにライフステージに応じて柔軟に対応できる家づくりが、長く満足できる二世帯住宅の鍵となります。
二世帯住宅に関連するよくある質問
二世帯住宅で完全分離タイプはいくらくらいしますか?
建物費用の目安は、およそ4,000万円〜7,000万円がひとつの目安となります。
ただし、これはあくまで目安であり、家の大きさ(延床面積)、依頼する建築会社(大手ハウスメーカーか工務店か)、設備のグレードによって費用は大きく変動します。
二世帯住宅が売れない理由は何ですか?
結論から言うと、買い手の需要が極端に少ないからです。
二世帯住宅は、玄関やキッチン、浴室などが2つある特殊な間取りのため、一般的な核家族にとっては広すぎたり、使い勝手が悪かったりします。
一世帯で住むには大規模なリフォームが必要になる場合が多く、その費用が購入のハードルを上げます。
二世帯住宅は固定資産税が軽減されるの?
はい、二世帯住宅は固定資産税が軽減される可能性が高いです。
特に、玄関や水回りがそれぞれ独立している「完全分離型」は、税制上のメリットが大きくなります。
その理由は、一定の要件を満たす二世帯住宅が、税法上「2戸の住宅」として扱われるためです。
これにより、税金の軽減措置が1戸分ではなく、2戸分適用されることになります。
「二世帯住宅」に関連する記事
二世帯住宅の費用相場は?タイプ別に価格目安や費用を抑えるポイントを紹介!
MEMBERSHIP
会員登録
sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。
おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。








![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)


